ドーパミン神経・欲望とセロトニン神経
東邦大学医学部・生理学第一講座(有田秀穂教授等)のHPに、セロトニン神経と痛み、セロトニン神経と腹式呼吸法(坐禅)の関係についての研究結果が記載されている。
有田教授らの研究から、腹式呼吸法などのリズム運動は、感情を制御するセロトニン神経を活性化させて、うつ病、自殺、パニック障害、摂食障害、あがり、子供などの「切れやすい」傾向、などを治癒させ、スポーツ・武道の向上を期待できるという。これは「欲望に関連するドーパミン神経の調節」である。
(13)「ダイエットを成功させるために」
(A)(要旨)
食欲や性欲などの本能的欲求が満たされた時、動物(人間も含めて)は快感を体験し、それに伴う生理的反応や行動が出現するようになります。この快の情動反応で主要な役割を果たすのがドパミン神経であり、それは中脳の腹側被蓋野という場所にあります。
セロトニン神経は欲望(食欲や性欲)に関連するドパミン神経をも抑制する。坐禅の呼吸法やジョギングなどのリズム運動で活性化されるので、無理なく、本能的欲望である食欲や性欲を調節できることになると言えます。それは、ダイエットを成功させることにも通じるものです。
(B)(HPから)
「一般に、食欲や性欲などの本能的欲求が満たされた時、動物(人間も含めて)は快感を体験し、それに伴う生理的反応や行動が出現するようになります。この快の情動反応で主要な役割を果たすのがドパミン神経であり、それは中脳の腹側被蓋野という場所にあります。確かに、餌を見せたり、性に関する匂いを嗅がせると、そのドパミン神経は興奮します。」
「さて、この欲望に関連するドパミン神経は、セロトニン神経によって抑制されることが動物実験で明らかにされています。すなわち、セロトニン神経が活性化されると、本能的欲望を抑制できるようになるのです。セロトニン神経は、坐禅の呼吸法やジョギングなどのリズム運動で活性化されることをこれまで説明してきましたが、その結果として、無理なく、本能的欲望である食欲や性欲を調節できることになると言えます。
「このように、セロトニン神経を呼吸法やジョギングなどのリズム運動で鍛えておくと、食欲や性欲などの本能的欲求を無理なく調節できるのです。ダイエットのために、欧米ではセロトニン関連の薬が使われているといわれますが、私は副作用のないリズム運動の実践をお勧めしたいと思います。」
(C)(考察)
セロトニン神経は欲望(食欲や性欲)に関連するドパミン神経をも抑制するというので、摂食障害の人は腹式呼吸法を中心としたカウンセリングをこころみるとよいだろう。過食も拒食も、無理な「欲求」によるから、認知のゆがみが関わる。だから、認知のゆがみの修正をおりこんだ腹式呼吸法とカウンセリングが効果的だろう。
うつ病や不安障害、非行・いじめ、依存症、などにも微妙な「欲望」(短絡的な安定物へのむさぼり)の心理が働いているので、腹式呼吸法を用いる仏教カウンセリングは、ドーパミン神経の調節にも効果的に働くのかもしれない。
統合失調症
なお、ドパミン神経は統合失調症にも関連すると言う説もあるが、仏教カウンセリングが統合失調症の症状の軽減に貢献できそうな理由は、セロトニン神経がドパミン神経を抑制することに関係しているかもしれない。
寛解期に入った患者が坐禅(呼吸法を中心としたやさしい坐禅でよい)をすれば、ストレスで再び悪化するのを防止するのにある程度貢献する。仏教カウンセリングでは、思いが浮かんでも、すぐ反応するのを止める訓練をするので、自動思考がわいた時にそれにすぐ反応せず受け流し、自動思考に振り回されて感情がひどくなるのを抑制できるからである。幻聴が、自分で考えた内容があたかも他人が言ったかのように感じる幻聴も、みだりに考えにおちることが少なくなれば(仏教カウンセリングでその訓練をする)、その種の幻聴は少なくなるわけである。
統合失調症の患者には、寛解期に入ったら薬物療法を続けながら、やさしい腹式呼吸法を行うことを勧めている。しかし、厳しく責めるタイプの「坐禅」は、これに向かない。統合失調症について理解のある指導者の指導が必要であることはいうまでもない。
(参照)
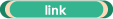 東邦大学医学部・生理学第一講座
→「元気」の神経
東邦大学医学部・生理学第一講座
→「元気」の神経
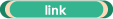 東邦大学医学部・生理学第一講座
→「元気」の神経
東邦大学医学部・生理学第一講座
→「元気」の神経